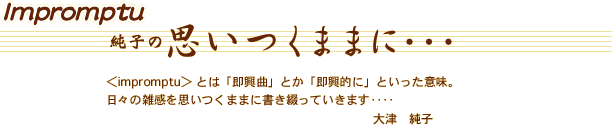 |
| <ちょっと遅いけど、謹賀新年!> | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2008年1月9日 記 |
|
あらら、又もや4ヶ月が流れてしまって・・・すっかりご無沙汰申し上げました。
さて、かなり遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます!
今、アメリカではいよいよ次期大統領予備選が始まり、新聞もTVも大騒ぎです。
昨年はついに、長年住み慣れたマンハッタンから車で2時間ちょっと東に行った、ロングアイランド(ここもまだニューヨーク州ですが)に居を移しました。ン十年の間にすっかり溜め込んでしまった物・もの・モノ・・・との闘いは想像を遥かに超える重労働でした。マンハッタンを去るにあたり、正直躊躇はあったのですけれど、学生時代から住んでいたアパートも何かと手狭になり、また、夏はマンハッタンより涼しいこの地で過ごすことも多かったから、ちょっとした"田舎"ペースも悪くないな、と。
でも、ゆったりペースに慣れちゃうと、感性の"退化"は猛スピードで訪れるものですねぇ。ついこの間まで、多種多様な人々の忙しない動き、大声、クラクション・・・といった街の喧騒すら"活気あるエネルギー"として吸収し、軽い足取りで駆け回っていたはずなのに、今やそれらは神経を逆撫でする"騒音"と化し、さらに、賑やかな場所に足を運ぶのが億劫になりだすと、行動も遅鈍化し、いつの間にかお腹や腰まわりに脂肪が・・・。キャ〜! と叫んでみても、すでに始まっているんですよねぇ、老化現象はシッカリと。 さて、1月8日付のNYタイムズ紙 The Arts セクションに、Bernard Holland氏(NY Times 音楽評論家)による、もの凄く面白い記事が載っていたのでご披露したいと思います。最近出版された、Kennith Hamilton著 『After the Golden Age』(Oxford University Press)からの引用を含めた記事なのですが、19世紀から20世紀の作曲家・演奏家・聴衆たちが演奏会にどんな態度で臨んでいたのか、様々な逸話が描かれていてお腹を抱えて笑ってしまいました。 クラシックのコンサートに行くと、演奏が行われている間じっと静かに息をこらしているのも辛く、曲の途中や楽章間で思わず拍手しちゃったりした時のバツの悪さったらない。何処かに穴を探してもぐり込みたい・・・なんて思いに駆られた体験をお持ちの方も多いかと思います。ご心配なさるな! フランツ・リスト(1811〜86:ハンガリー生まれで、19世紀最大のピアノ・ヴィルトゥオーソ)やアントン・ルビンシュタイン(1829〜94:リストと並び称賛されたロシアのピアニスト)といった巨匠たちは、曲の楽章間に拍手がないと不機嫌だったそうですし、演奏の最中であっても、聴衆が熱狂して拍手喝さいが起こることを大いに期待していたらしい。ベートーヴェンですら"We want applause."(拍手を!)と述べていたとのことだけれど、尤も彼の時代には1回のコンサートの場で、彼のソナタを全楽章演奏する演奏家なんていなかったのだとか。えっ〜!?
当時は、コンサート自体が今のように"ワンマン・ショー"(笑)のような形態ではなくて、ボードビル(演芸寄席)の"バラエティ・ショー"のようなもので、オペラの幕間やシンフォニーの楽章間に、ピアニストやヴァイオリニスト、歌手、カルテットやらトリオやらが入れ替わり立ちかわり登場しては演奏をする、というのが慣例だったそうなのです。 "one man, one recital"といった演奏会を開くことができたのはリストぐらいだったとか。彼は演奏合間には自分の有力後援者の到着を会場入口で出迎えたり、聴衆の中に混じってお喋りしてたっていうんですから余裕シャクシャク。そういった「お客様中心」のサービス満点ぶりはショパンにも当てはまり、自作のホ短調・コンチェルトを1830年にワルシャワで演奏した際、最初のふたつの楽章の合間にまったく違う曲を挟み入れてご披露していた、とのこと。こんな演奏家によるサービス熱は中途半端じゃなくて、あの"神聖な"ともいえるベートーヴェンのヴァイオリン・コンチェルトの、1806年ウィーン初演においては、なんとソリストがplaying his violin upside down(・・・とあるが、どういうことだ? ヒッチャカメッチャカ=自由奔放に演奏したってことかしら? まさかヴァイオリンを上下逆さに持って弾いたわけではないだろうし)で、しかもたった1本の弦で弾きまくり、聴衆を大いに沸かせていた・・・てな話でして、さて、何と申しましょうか・・・世は奇なり、ですかな。 当時、一世を風靡していた超絶技巧の"魔のヴァイオリニスト"、ニコロ・パガニーニ(1782〜1840:イタリア生まれ。聴衆が熱心に耳を傾けないことに腹を立て、ヴァイオリンの弦を3本切って残った1本の弦だけで演奏し、聴衆が熱狂したという逸話は有名)を崇める風潮が反映していたのかもしれませんが、ふ〜ん、あのベートヴェンの曲をねぇ・・・と信じがたい思いではあります。でも、パガニーニの、その見事な技巧はヨーロッパ中の聴衆を魅了し、その演奏には同時代の作曲家の多く(シューベルトやシューマン、リストなども)が感銘を受けて、彼の作品を編曲し、また、新たに書き上げた曲を彼に捧げたりしていたんですよね。 まぁ、聴衆が身じろぎもせず、演奏家の一挙一音を逃すまい、と聴き耳をたて、真剣刃で迫ってくるような現代のクラシック・コンサート風景では、演奏家もチャラチャラと聴衆にウィンクしながら(笑)遊んでるってわけにはいかないけれど、「音楽会」というものが如何に<娯楽>であったかが分かって面白いですね。
「暗譜」して演奏するということは現代と同じく、1800年代においても尊ばれてはいたものの、ショパンやベートーヴェンなどはスコアを前に置いて演奏することが作品に対する評価をより高める、と考えていたのだとか。アントン・ルビンシュタインは、完璧に暗譜している曲であっても、演奏中に記憶が"失踪"(笑)してしまうことがよくあったそう。
また、19世紀には"作曲家が記述した"とおり、"スコアに忠実"に演奏することはそれほど重要な「案件」ではなくて、むしろ聴衆にこの音楽がどれだけ難しいものであるかを知らしめるためには、時折"clinker"(間違えた音)を入れて演奏したらよい、と、ハンス・フォン・ビューロー(1830〜1894:19世紀の著名なドイツ人指揮者・ピアニスト。リヒャルト・シュトラウスを見出した)は生徒に話していたのだとか。嬉しくなるのは、当時の演奏家も聴衆も誰一人として"ミス"なんか気にしなかった、ということ。 というわけで、こんな楽しい記事にお正月早々遭遇し、多少のミスなんか気にしなくたっていいんだよね〜・・・と、私はすっかり明るい気分になっちゃった(笑)のであります。今年はいい年になるぞ〜ぉ! | ||
| 過去のエッセイ集リストへ |
| Impromptu TOPへ |