2002年6月号

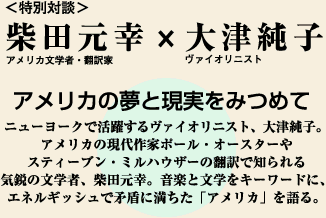

| 『CAMPANELLA』 2002年6月号 |
 |
|
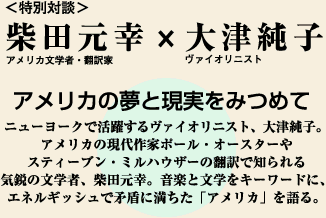 |
||
 |
||
| 大津純子の新プロジェクト「アメリカン・ルネッサンスからジャズ・エイジへ(19世紀半ば〜1920年代)」の第一回コンサートに、柴田元幸氏は音楽評論家の黒田恭一氏とともにゲストとして参加。演奏の合間に、その時代のアメリカのエピソードを披露して楽しませてくれた。「アメリカ」という共通項を持つ大津、柴田の二人が、アメリカ談義を繰り広げる。 | ||
| ■ヨーロッパとの距離感 | |
| 柴田: | 僕はクラシックは全然分からないけれども、今回のコンサートは、すごく珍しいラインナップだったじゃないですか。 |
| 大津: | この企画は2年前から考えていたものなんですが、「誰と」「どのように」作り上げていったらいいのか、ずいぶん悩みました。その結果、選曲は黒人霊歌やフォスター、ゴトシャルク、女性作曲家のエイミー・ビーチ、逆にヨーロッパの作曲家でアメリカに影響を受けたディーリアスやドヴォルザークとなりました。私が今回取り上げたこの時代は、アメリカがヨーロッパ文化の影響から離れ、独創性や「個」としての人間性を求めて、夢と希望に溢れていた「素敵な時代」。以前から注目していたんです。 |
| 柴田: | アメリカという国のいい意味での折衷的な感じが、拝聴していて実感としてよく分かりましたよね。ヨーロッパの高尚な音楽が土着的なものと出会ったときの、あの混ざり方とかね。 |
| 大津: | 長くアメリカに住んでみると、日本でのアメリカ文化の紹介のされ方に偏りがあるのが気になって……。 「アメリカ =(イコール)歴史の浅い国」そして「アメリカ =(イコール)ポップカルチャー」。やっぱりジャズやミュージカルが主軸でしょう?それに日本の人には「フランス音楽をやるならフランス人、ドイツ音楽をやるならドイツ人が絶対」っていうのがすごくあるんですね。なんでそうなんだろう、とずっとギャップを感じていたんです。アメリカにいるとそれをあんまり感じない。なぜなら、アメリカにはヨーロッパの土台があるからなんですね。 |
| 柴田: | うん、それはちょっとうかがいたかったんですけど。たとえば映画やポピュラー音楽だったら、アメリカが後発だという意識は当然ない。だけどクラシックに関しては、アメリカは後発というか、遅れているというイメージが日本ではありますよね。アメリカのクラシックの音楽家たちには、「本物はヨーロッパにある」という意識はないんですか。 |
| 大津: | ヨーロッパに対するコンプレックスは、やっぱりありますね。けれどもヨーロッパの人にも、伝統的な因習から脱け出して、自由な活動を求めてアメリカにやって来た音楽家もいるし、そういう人たちがニューヨークに来て、ジュリアード音楽院でも教えている。だから日本にいるよりも(ヨーロッパへの)距離はずっと近く感じますね。 |
| 柴田: | なるほど。ヨーロッパの延長でもあり、ヨーロッパにない自分自身もあると。黒田恭一さんもおっしゃってたけど、音楽には演奏家と作曲家がいる。再現する人と作る人と、両方いるんですよね。対して、文学は作家だけ。だから文学の分野では、イギリスやヨーロッパとの断絶感があるというか、「自分たちは違うことをやるんだ」という意識がものすごく強い。音楽の場合、そこに演奏家という存在があることで、引き継ぐ要素が強いんでしょうね。 |
| 大津: | 再現者としての演奏家は、やっぱりいろんな文化を吸収して表現の幅を広げたい、という意識が強いですね。ところで、コンプレックスといえば、アメリカ社会は見事に階層化されていますけれど、たとえば上流社会に属する人たちの中には、ヨーロッパへの憧れが強くて、ヨーロッパ女性と結婚している人も結構 いますね。 |
| 柴田: | だから、そういう意味での、ヨーロッパとアメリカの見えない上下関係みたいなものと、クラシック音楽とたとえば黒人霊歌のような土着的はものとの見えない上下関係が、対応している気がするんですよね。で、この間のコンサートを聴いていて、やっぱり思ったのは、アメリカのいい部分っていうのは、要するに、両者が「出会う」というところだろうなと。 |
| 大津: | まずは受け入れてみましょう、という精神がありますよね。 |
| 柴田: | 柴田:住み分けがないんですね。高尚なものと、俗っぽいものが、いとも簡単に出会ってしまうのがアメリカ。 芸術で「正解」を言い出すとロクなことはないんですが、アメリカはそういう意味ではね、こと芸術に関しては「正解」という発想があまりない国だろうと思いますね。 |
| ■「古き良きアメリカ」の時代へ | |
| 柴田: | 19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、ヨーロッパ人がアメリカに何か新しいものを見つけていく、その場合に、黒人音楽だとか大自然だとか、むしろ文明社会の周辺におかれた人たちや物が文化のエネルギーになっている。そこが多分、アメリカの強みだったんじゃないかと思う。ヨーロッパから夢見られる存在である自分たちも、同時にアメリカに夢を見ているという。 |
| 大津: | そうですね。アメリカが一番元気だったのが、その頃じゃないでしょうか。 |
| 柴田: | 20世紀になると話がどんどんややこしくなるのは、作家マーク・トウェインの時代あたりから、だんだんフロンティアがなくなって、奴隷制も形の上では廃止されて……。簡単に言ってしまうと、敵の姿がはっきりしないぶん戦いづらくなって、「ここ」に価値があるというのも認めづらくなる。 |
| 大津: | たしかにそれは言えるでしょうね。 |
| 柴田: | 多分、最後に「ここに新しいものがある」っていうのが、60年代の「月」でしょうね。あとは、同じ60年代にヒッピーが東洋にかぶれたりもしたけれど、それはもう、ヨーロッパがアメリカを見て、「ここに新しいものがある」と思ったのに比べると、ずっと小さくて。まさに、スコット・フィッツジェラルドの小説《グレート・ギャッツビー》の中にある「人類最後の大きな夢がアメリカにあった」という感じはもうない。(フィッツジェラルドの生きた)20年代は、華やかで賑やかで混沌としていて、けれどもそこには終焉を予感するような暗さもある。この後になると、世界がどんどんアメリカ化していって。 |
| 大津: | 私はやっぱり、今こういう時代だからこそ、アメリカの「古き良き時代」をもう一度見つめてみたいという気持ちが強かったですね。 |
| 柴田: | そうですね。やっぱり、去年の9月11日(テロ事件)以降の一連の出来事を考えると、アメリカにもまずい面というのはある。この国は、「いいものは何でも受け入れよう」という姿勢があるときはとてもいい。でも自分たちが「正解」を持っていると思い込むと、かなり何というか、はた迷惑なところもある。ただ、最初は声を上げにくかった良識的な人たちも、そのうち表に出てくるだろうと思いたいですね。 |
| 大津: | ええ。私は、アメリカという国には、強さと共に、バランスの取れた健全な精神があると信じています。 |
| ■アメリカとの出会い | |
| 柴田: | ところで、大津さんはどうしてアメリカに行くことになったんですか。 |
| 大津: | 私は芸大を出た後、やっぱりヨーロッパで勉強したいと思って、ドイツ語やフランス語のレッスンをとっていたんですが、たまたま知り合いの先生から、ジュリアードのドロシー・ディレイという高名な先生に紹介されて、急に方向転換してアメリカに行くことになったんです。ですからしばらくは英語でかなり苦労しました。先生はどうしてアメリカ文学に? |
| 柴田: | 僕はね、いい加減なもんで、大学にアメリカ文学でとてもいい先生がいたという、それだけなんですよ。でも結果的にそれで良かったなと思うのは、まあ学者って、自分が専攻している国の国民性を滑稽なくらい模倣するんですね。たとえばフランス文学やってるとエゴイストが基本形で、ドイツ文学やってる奴は永遠の文学青年みたいな。で、イギリスは伝統に忠実で、伝統に逆らうにしても伝統の大きさを認めてはいる。でも、アメリカはみんな自分勝手で無反省、これは自分に合っている……。 |
| 大津: | あはは(笑) |
| 柴田: | 文化の流れはあるんだけど、ヨーロッパみたいに伝統が積み重なるということがなくて、つねに一からはじめるという、あれがやはり強みだろうと思いますね。だから伝統じゃないんですよね。アメリカの場合は。 |
| ■垣根のない音楽の世界 | |
| 大津: | 今回コンサートでご一緒したジャズピアニストの佐藤允彦さんとは、5年ほど共演させていただいていますが、彼との出会いは、私の音楽観を変える大きなインパクトになりましたね。ジャズ音楽の奥行きや民族音楽の多彩さ面白さは、まさに目からウロコ。彼の普遍的な垣根のない世界を体験して、それが私のクラシック音楽に接するときの視野を広げることにもなりました。 なにより楽しくって、「いいものはいい」、音楽全体をそういう風に見られるようになりましたね。 |
| 柴田: | シリーズ第2回は、チャーリー・チャップリンですよね。 |
| 大津: | 私はチャップリンの映画が大好きだし、アメリカにおいてハリウッドが夢のような存在だった、その時代に彼の目を通して触れてみたいなと。 |
| 柴田: | 20年代というのは、アメリカが絶望的に明るかった時代で、それはフィッツジェラルドの小説にも現れている。その後の30年代は、みんながお腹を空かせていた時代で、それがチャップリンに象徴されている。でもそれだけじゃなくて、そこにはいろんな視点があると思うので、次回のコンサートが本当に楽しみですね。 |
| 大津: | みなさんにアメリカ文化紹介を「ライフワークにしたら?」なんて言われるんですけれど、まずは、この4回のシリーズを成功させたいと思ってます。 |